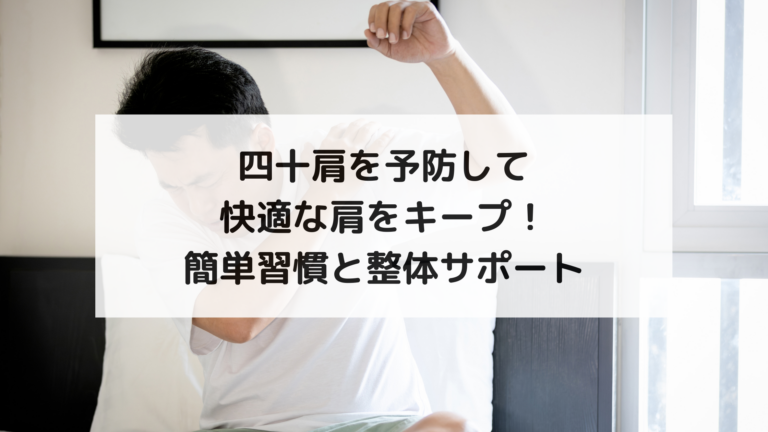- update更新日 : 2025年09月20日
folder未分類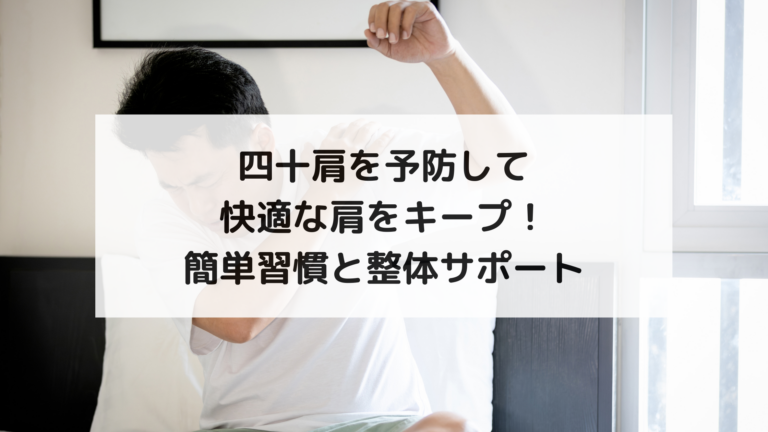
1. 四十肩とは何か

1.1 四十肩の症状と原因
四十肩(しじゅうかた)は、肩の関節や周囲の筋肉・腱(けん)が硬くなり、動かすと痛みが出る症状です。特に40歳前後で発症しやすいことからこの名前が付いていますが、実際には30代後半から50代でもよく見られます。
主な症状は次の通りです。
- 肩を上げたり後ろに回したりすると痛む
- 夜間に肩の痛みで目が覚める
- 髪を結ぶ、服を着るといった日常動作がつらい
- 動かせる範囲が狭くなり、肩が硬く感じる
症状の進行は大きく3段階に分けられます。
- 急性期(痛みが強い時期):肩を動かすだけで痛みが出て、夜間痛も伴うことが多いです。
- 凍結期(肩が硬くなる時期):痛みは少し和らぎますが、肩の可動域(かどういき)が狭くなり、日常動作が制限されます。
- 回復期(動かせるようになる時期):痛みは軽くなり、徐々に肩を動かせる範囲が広がりますが、完全に元に戻るまでには数か月かかることもあります。
原因は明確に1つではなく、肩関節周囲の腱や筋肉の炎症、関節包の硬化、日常生活での肩の使い方 などが複合的に関わります。特にデスクワークやスマホ操作で肩を前に出す姿勢が続くと、肩の柔軟性が失われ、四十肩になりやすくなります。
たとえば、デスクで長時間パソコン作業をしていると、知らず知らずのうちに肩が前に巻き込まれ、肩の関節の動きが制限されることがあります。これにより、肩を上げる・後ろに回す動作が日常的にしにくくなり、軽い痛みから始まって徐々に症状が悪化することがあります。
四十肩は放置しても自然に治ることがありますが、痛みが長引くと日常生活に支障をきたすため、早めの予防やケアが大事です。
1.2 四十肩になりやすい人の特徴
四十肩は誰でも起こる可能性がありますが、生活習慣や体の使い方によってなりやすい人の特徴があります。自分の生活に思い当たる点があるかチェックしてみてください。
長時間のデスクワークやスマホ操作
肩を前に出す姿勢が続くことで、肩の関節周囲の筋肉や腱が硬くなります。たとえば、通勤電車でスマホを見続けるだけでも、肩の柔軟性が徐々に失われることがあります。
運動不足で肩周りの筋肉が弱い
肩の筋肉は腕を支え、動かすために必要です。運動不足で肩や背中の筋力が低下すると、関節の負担が増え、炎症(えんしょう)や痛みが起こりやすくなります。
肩や腕を偏った使い方している
片方だけで荷物を持つ、重いカバンを同じ肩でかけるなど、肩に負担をかけ続ける動作は四十肩リスクを高めます。特に利き腕ばかり使っていると、肩の動きがアンバランスになりやすいです。
ストレスや睡眠不足が多い
ストレスや睡眠不足は肩の筋肉を緊張させ、血流が悪くなります。結果として肩関節の動きが制限され、痛みや硬さにつながることがあります。
加齢による関節や腱の変化
40代前後から肩の腱や関節包(かんせつほう)が硬くなりやすく、肩の柔軟性が低下します。これにより、些細な動きでも痛みが出やすくなります。
注意点
- 筋肉や関節の硬さを放置すると、肩の可動域がさらに狭くなり、日常生活での動作が制限されることがあります。
- 特に肩を上げる・後ろに回す動作がつらくなるため、服を着る、髪を結ぶ、荷物を持つといった日常の基本動作が難しくなることがあります。
たとえば、朝にシャツを着るときに片腕だけしか上がらず、着替えに時間がかかるケースがあります。これが続くと、仕事や家事の効率も落ちてしまい、ストレスが増える原因になります。
四十肩になりやすい人は、日常生活の中で肩をこまめに動かすこと、肩周りの筋力を維持することが予防につながります。
2. 四十肩を予防する生活習慣

2.1 日常生活の簡単な予防策
四十肩(よんじゅうかた)の予防は、特別な運動や高額な器具がなくても、日常生活のちょっとした工夫で大きな効果が期待できます。ここでは、毎日取り入れやすい簡単な予防策を紹介します。
- 肩を動かす習慣をつくる
- 家事や仕事の合間に、肩を前後や回す軽い運動を数回取り入れるだけでも、関節の柔軟性を保てます。
- 「テレビを見ながら肩を回す」「歯磨き中に肩を上げ下げする」など、短時間でできる動作を意識しましょう。
- 荷物の持ち方に注意する
- 重い荷物を片方の肩だけで持つと、肩の筋肉に負担がかかり四十肩のリスクが高まります。
- 可能であれば両手で持つかリュックを使用することで、肩への負担を分散できます。
- 無理な姿勢を避ける
- デスクワークやスマホの長時間使用は、肩や首に負担をかけやすいです。
- 1時間ごとに肩を回す、軽くストレッチするなど、簡単な休憩を取り入れることが大切です。
- 入浴で肩を温める
- お風呂で肩を温めることで血流が良くなり、筋肉が柔らかくなります。
- 血流の改善は、肩関節の動きをスムーズにし、四十肩予防につながります。
2.2 姿勢や動作のポイント
四十肩(よんじゅうかた)は、肩関節や周囲の筋肉に負担がかかることで発症しやすくなります。日常生活で正しい姿勢と動作を意識することは、肩の痛みを予防するために非常に重要です。
- デスクワーク時の姿勢
- 背中を丸めず、背筋をまっすぐに保つことが大切です。
- モニターは目の高さに合わせ、肩や首に余計な負担がかからないようにしましょう。
- 腕や肩は力を抜き、肘は90度を目安に机に置くと自然な姿勢を維持できます。
- 立ち姿勢のポイント
- 立っているときも、肩が前に巻かないように胸を開き、肩甲骨を軽く引き下げることを意識します。
- 片足に体重をかけ続けず、左右の足に均等に体重を分散させることも大切です。
- 物を持ち上げる動作
- 重い物を持つときは、肩だけで持たず脚の力を使って腰を落として持ち上げるようにします。
- 腕を伸ばして肩に負担をかける動作は控え、持ち上げる高さや角度を調整することで肩への負担を減らせます。
- 日常の動作の意識
- 高い棚に手を伸ばすときは、台に乗るなど体全体を使い、肩だけで無理に伸ばさない。
- 電話を肩に挟むのではなく、ハンズフリーやスピーカーフォンを活用するなど、肩に負担をかけない工夫を取り入れます。
2.3 食事や栄養でのサポート
四十肩(よんじゅうかた)の予防には、肩関節や筋肉の健康を支える栄養バランスも重要です。運動や姿勢の改善だけでなく、食事からも肩の強さをサポートしましょう。
- タンパク質で筋肉をサポート
- 肩周りの筋肉を維持・強化するためには、十分なタンパク質が必要です。
- 鶏肉、魚、大豆製品(豆腐・納豆)、卵などを毎日の食事に取り入れましょう。
- カルシウムとビタミンDで骨を強化
- 肩関節を支える骨の健康にはカルシウムが不可欠です。
- 牛乳、チーズ、ヨーグルト、小魚などを意識して摂取し、日光浴でビタミンDを補うと吸収が良くなります。
- 抗炎症作用のある栄養素
- 肩の炎症や痛みを和らげるには、オメガ3脂肪酸やビタミンEが有効です。
- サバやサーモンなど青魚、ナッツ類、アボカド、オリーブオイルなどを取り入れると良いでしょう。
- 水分補給も忘れずに
- 筋肉や関節の柔軟性を保つために、水分を十分に摂ることも重要です。
- 一度に多く飲むのではなく、こまめに水やお茶を飲む習慣をつけましょう。
- バランスの良い食事が基本
- 肩だけでなく全身の健康を支えるため、野菜や果物も取り入れて抗酸化作用を高めます。
- 食事の偏りを防ぎ、三食きちんと摂ることで筋肉や関節の回復力を高められます。
3. 自宅でできるストレッチ・運動

3.1 肩関節の柔軟性を保つストレッチ
四十肩(よんじゅうかた)予防には、肩関節の柔軟性を維持することが非常に重要です。無理なく毎日続けられるストレッチで、肩の動きを滑らかにしましょう。
- 肩回しストレッチ
- 両肩をゆっくり前に回した後、後ろに回します。
- 1セット10回を目安に行い、肩の可動域を広げます。
- 無理に大きく回さず、痛みのない範囲で行うことがポイントです。
- 腕上げストレッチ
- 両腕をまっすぐ上に伸ばし、ゆっくり頭上で手を合わせます。
- 息を吐きながら腕を伸ばし、肩甲骨周りを軽く意識します。
- 10秒~20秒キープし、2~3回繰り返すと効果的です。
- 壁スライド
- 壁に背中をつけ、両腕を肩の高さで壁に沿わせて上下に滑らせます。
- 肩関節や肩甲骨の動きを自然に広げる運動です。
- 腰や背中が反らないよう注意して行いましょう。
- タオルを使ったストレッチ
- タオルを両手で持ち、背中の後ろで上下に動かします。
- 肩の前後や肩甲骨周りの柔軟性を高めるのに効果的です。
- 痛みが出る場合は無理せず範囲を狭めて行います。
- ストレッチの継続がカギ
- 毎日少しずつ行うことで肩関節の柔軟性を維持できます。
- 運動前のウォーミングアップとしても有効です。
- 痛みが強い場合は無理せず、軽い動きから始めることが大切です。
3.2 筋力を鍛える簡単トレーニング
肩関節周りの筋力を鍛えることで、四十肩(よんじゅうかた)の予防効果が高まります。ここでは自宅で簡単にできるトレーニングを紹介します。
- ペットボトル肩上げ運動
- 500ml~1Lのペットボトルを両手に持ち、肩の高さまで腕を上げ下げします。
- 10回を1セットとして、1日2セット行うと肩の筋力維持に効果的です。
- 肩に痛みがある場合は重さを軽くするか、動作をゆっくり行いましょう。
- 壁プッシュアップ(膝つき)
- 壁に手をつき、腕を曲げて胸を壁に近づけ、ゆっくり戻します。
- 10回を1セット、1日2~3セットが目安です。
- 肩に負担が少なく、胸・肩・腕の筋肉をバランスよく鍛えられます。
- タオルを使った肩引き運動
- 両手でタオルを持ち、前から頭上に持ち上げたり、背中で上下に動かしたりします。
- 肩関節や肩甲骨周りの安定性を高め、柔軟性と筋力を同時に鍛えられます。
- 息を止めず、ゆっくり動かすことがポイントです。
- サイドレイズ(軽めの重りで)
- 軽いダンベルやペットボトルを両手に持ち、腕を横に上げて肩の高さまで持ち上げます。
- 10回を1セットとして、1日1~2セット行います。
- 肩に痛みがある場合は回数を減らすか、腕の高さを下げて行います。
- 継続のコツ
- 1日5~10分でできる運動を習慣にすると、肩の安定性が向上します。
- 運動後は軽くストレッチをして筋肉をほぐすことが重要です。
- 無理せず、自分のペースで行うことが長続きの秘訣です。
3.3 運動を続けるコツと注意点
肩の筋力や柔軟性を維持するには、無理なく運動を続けることが大切です。ここでは継続するためのポイントと注意点を紹介します。
- 毎日のルーティンに組み込む
- 朝起きたときやテレビを見ながらなど、生活の中で習慣化すると忘れにくくなります。
- 1日5分でも継続することが、肩の健康維持につながります。
- 無理のない負荷で行う
- 筋肉痛がひどくなるほど重い負荷は避け、軽めのダンベルやペットボトルで十分です。
- 肩に痛みがある場合は、無理に動かさず休むことも重要です。
- 正しいフォームを意識する
- 間違った姿勢で運動すると、肩や首を痛める原因になります。
- 鏡で姿勢を確認したり、ゆっくり動かすことで安全に運動できます。
- 週に数回の休息日を設ける
- 筋肉の回復のため、毎日激しい運動をする必要はありません。
- 週に1~2回の軽い休息日を設けることで、肩の負担を減らせます。
- 体調や痛みに応じて調整する
- 疲れや痛みが強い日は無理せず運動量を減らすことが、長く続けるコツです。
- 痛みが改善しない場合は、専門家(整体や整形外科)に相談しましょう。
4. よくある失敗とその対策
4.1 無理な運動による肩の痛み
肩の運動は四十肩(よんじゅうかた)の予防に効果的ですが、無理に行うと逆に痛みや炎症を引き起こすことがあります。ここでは、よくある失敗例とその対策を解説します。
- 過度な負荷や急な動き
- 重いダンベルや急な肩のひねりは、肩関節や筋肉に負担をかけます。
- 初めは軽めの負荷で、ゆっくりとした動きで行うことが大切です。
- 痛みを我慢して続ける
- 運動中や翌日に痛みが強くなる場合は、中止して休むことが必要です。
- 「少しの痛みなら大丈夫」と我慢すると、炎症や肩の拘縮(こうしゅく)が進むことがあります。
- ウォームアップ不足
- 運動前に肩周りのストレッチや軽い回旋運動を行わないと、筋肉や関節を痛めやすくなります。
- 5分程度のウォームアップを行い、関節を温めてから運動を始めましょう。
- 正しいフォームを意識しない
- 腕を無理に上げる、肩をすくめるなどの動作は、肩関節に過剰な負担をかけます。
- 鏡でフォームを確認したり、最初は少ない回数で行うと安全です。
- 回復を考えず連日運動する
- 筋肉や関節には回復時間が必要です。休息日を設けず連日運動すると、肩痛が慢性化することがあります。
- 週に1~2日は軽めの運動日や休息日を設けましょう。
4.2 長時間の同じ姿勢による悪化
肩や首のこりは、日常生活での姿勢が大きく影響します。特にデスクワークやスマホ操作で同じ姿勢が続くと、肩関節や周囲の筋肉に負担がかかり、四十肩(よんじゅうかた)のリスクが高まります。
- 長時間のデスクワーク
- PC作業で背中が丸まり、肩が前に出た姿勢が続くと、肩の筋肉が硬くなります。
- 1時間ごとに肩回しや軽いストレッチを取り入れることが予防につながります。
- スマホ・タブレットの見すぎ
- 顔を下に向けた状態が長く続くと、首や肩の筋肉に負担がかかります。
- 画面は目の高さに合わせ、定期的に頭を上げて首を伸ばすことを意識しましょう。
- 運動不足による筋力低下
- 同じ姿勢で固まると肩周りの筋肉が弱くなり、肩関節の安定性が低下します。
- 軽い肩の運動や肩甲骨まわりのストレッチで、筋肉をほぐすことが重要です。
- 座り方や椅子の高さの影響
- 椅子が高すぎたり低すぎたりすると、肩に余計な負荷がかかります。
- 肘が90度になる高さ、背筋をまっすぐ保てる椅子を選ぶと肩への負担が軽減されます。
4.3 予防策を中断してしまうケース
四十肩(よんじゅうかた)の予防には、日常生活でのストレッチや運動の継続が欠かせません。しかし、多くの人は「忙しい」「面倒」と感じて予防策を中断してしまい、再び肩の痛みに悩むことがあります。
- 運動習慣が定着していない
- 毎日少しずつ行う簡単な肩のストレッチでも、続けることが大切です。
- カレンダーにチェックを入れる、スマホのリマインダーで習慣化すると中断を防げます。
- 効果を実感する前にやめてしまう
- すぐに改善が見られないと、モチベーションが下がることがあります。
- 目安として、肩の動きや痛みが改善するまでには数週間~1か月かかることを理解しましょう。
- 生活環境や仕事の忙しさ
- 出張や残業、家事などで時間が取れない場合があります。
- 1回5分程度の簡単な運動でも効果はあるため、短時間でも続けることが大切です。
- 無理な目標設定
- 毎日30分の運動やハードなトレーニングを設定すると、続かない原因になります。
- 無理のない簡単な運動から始め、徐々に負荷を増やす方法がおすすめです。
5. いしざい整体院でのサポート
5.1 四十肩予防・改善に対応した施術
いしざい整体院では、四十肩(よんじゅうかた)の予防と改善に特化した施術を提供しています。肩の痛みや可動域の制限は、日常生活に大きな影響を与えるため、早めの対応が重要です。
- 個別カウンセリングで原因を特定
- 患者さん一人ひとりの肩の状態や生活習慣を丁寧に確認します。
- 痛みの原因や姿勢の歪み、筋肉の緊張を把握したうえで最適な施術プランを提案。
- 痛みの少ない無痛施術
- バキバキしない優しい手技で、肩関節や周囲の筋肉をほぐします。
- 初めての方や痛みに敏感な方でも安心して受けられます。
- 肩の動きを改善するアプローチ
- 関節の柔軟性を高めるストレッチや筋肉のバランスを整える施術を組み合わせます。
- 継続的に施術を受けることで、肩の可動域が改善し、四十肩の予防効果が期待できます。
- 生活習慣のアドバイス
- 日常生活での姿勢や動作のポイントもアドバイス。
- 自宅でできる簡単なストレッチや運動を取り入れることで、施術効果を持続させます。
5.2 無痛で安心の手技とカウンセリング
いしざい整体院では、痛みを伴わない優しい手技と丁寧なカウンセリングを重視しています。肩の痛みや四十肩の症状に悩む方でも、安心して施術を受けられる環境が整っています。
- 痛みの少ない手技
- バキバキ鳴らす施術ではなく、関節や筋肉に優しい圧をかけてほぐす方法を採用。
- 初めて整体を受ける方や、痛みに敏感な方でも安心。
- 個別カウンセリング
- 肩の痛みの原因や生活習慣を詳しくヒアリング。
- その情報をもとに、最適な施術プランを提案し、患者さんの不安や疑問にも丁寧に回答。
- 施術の進行を体感できる
- 「何をされているか分からないほど優しい」と感じる患者さんが多く、リラックスしながら施術を受けられます。
- 無理に力を加えないため、施術中の負担が少なく、肩の動きがスムーズに改善。
- 生活への応用アドバイス
- 日常生活での肩の使い方やストレッチ法も合わせて指導。
- 施術だけでなく、自宅でのケアも取り入れることで、肩の痛みを再発させにくくします。
5.3 アフターケア指導で継続的に予防
いしざい整体院では、施術後のアフターケア指導を重視しています。肩の痛みや四十肩を改善するだけでなく、再発を防ぎ、日常生活で快適に過ごせるようサポートします。
- 院長自らの指導
- 施術を担当する院長が、個々の症状や生活習慣に合わせたアフターケアを直接指導。
- 根拠に基づいた具体的な方法で、効果的に肩を守ります。
- 自宅でできるストレッチ・運動
- 施術後の肩の可動域や筋力を維持するための簡単なストレッチや運動を紹介。
- 生活の中で取り入れやすく、無理なく続けられる内容です。
- 日常生活での注意点
- 肩に負担をかけない姿勢や動作のコツを指導。
- 仕事や家事の中で肩を守るポイントを具体的に教えてもらえるので、再発予防につながります。
- 継続的な健康管理
- 定期的な通院やセルフケアの組み合わせで、肩の痛みを長期的に予防。
- 「施術+アフターケア」の両輪で、肩の健康を維持し、快適な生活をサポートします。
6. まとめ:四十肩予防のポイント
6.1 生活習慣・運動・整体の三本柱
四十肩の予防・改善には、一つの方法だけではなく、生活全体を見直すことが重要です。いしざい整体院では、以下の三本柱で肩の健康をサポートします。
- 生活習慣の改善
- 正しい姿勢を意識し、肩に負担をかけない日常動作を心がけます。
- 長時間同じ姿勢を避け、休憩や肩の軽いストレッチを取り入れることが大切です。
- 運動による筋力と柔軟性の維持
- 肩周りの筋肉を無理なく鍛え、可動域を保つストレッチやトレーニングを継続。
- 適度な運動は血流を促し、肩の痛みやこわばりを予防します。
- 整体施術によるサポート
- 無痛で優しい施術により、肩や背中の筋肉の緊張を和らげ、関節の動きを改善。
- 日常では気づかない身体の歪みやクセも調整し、再発を防ぎます。
この三本柱をバランスよく組み合わせることで、四十肩のリスクを大幅に減らし、肩の健康を長期的に維持することが可能です。
6.2 早めの予防で快適な肩をキープ
四十肩は、症状が軽いうちに対策を始めることで、進行を防ぎ、快適な肩の動きを維持できます。ポイントは「予防の習慣化」です。
- 違和感を感じたら早めに動かす
- 肩に軽いこわばりや痛みを感じたら、無理のない範囲でストレッチや運動を取り入れましょう。
- 放置すると症状が悪化し、回復までに時間がかかることがあります。
- 生活習慣を見直す
- 長時間の同じ姿勢や、肩に負担をかける動作を避ける。
- 日常生活の中で肩を休める時間を意識的に作ることが大切です。
- 専門家によるチェックと施術
- いしざい整体院では、肩の可動域や筋肉の状態を確認し、無理なく改善できる施術を提供。
- 早めに施術を受けることで、慢性的な肩の痛みや動かしにくさを防ぎます。
四十肩は年齢とともに発症リスクが高まりますが、早めに対策を習慣化することで、肩の快適さを長く維持できます。
日常生活の工夫と整体サポートを組み合わせ、肩の健康をしっかり守りましょう。
四十肩になる前に始める、安心の肩ケアなら、いしざい整体院へ
日常の姿勢や運動に加えて、整体院でのサポートを取り入れることで肩の健康をしっかり守れます。まずは予約ページから簡単に相談して、あなたの肩を守る一歩を踏み出しましょう。
ホームページはこちら